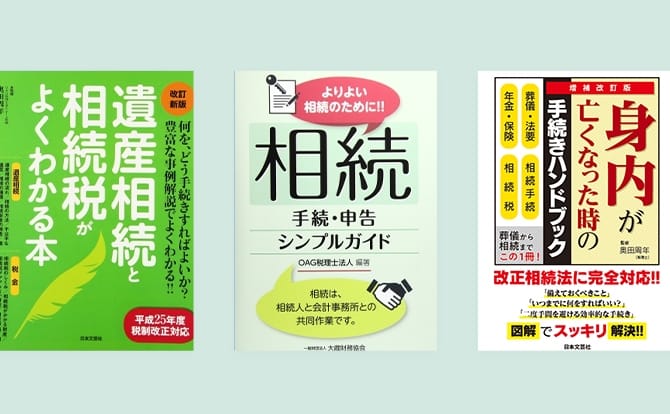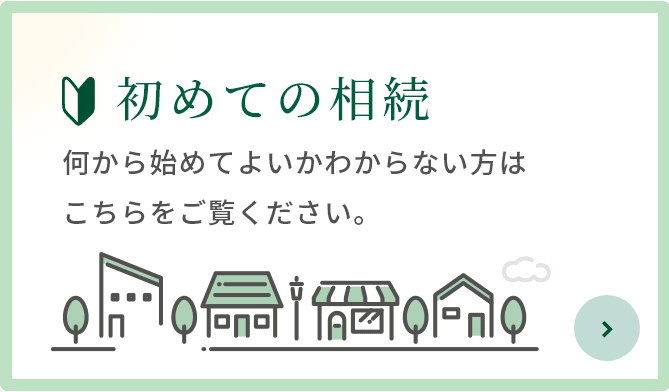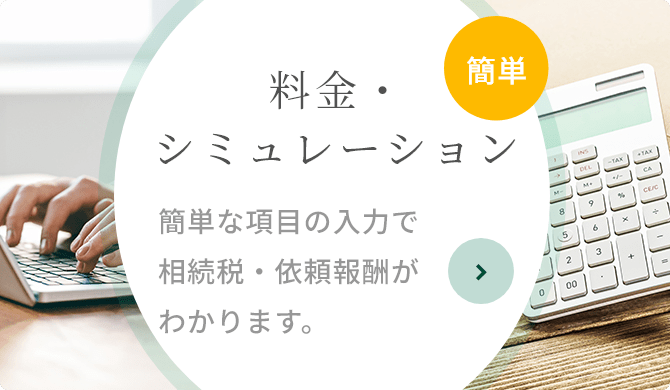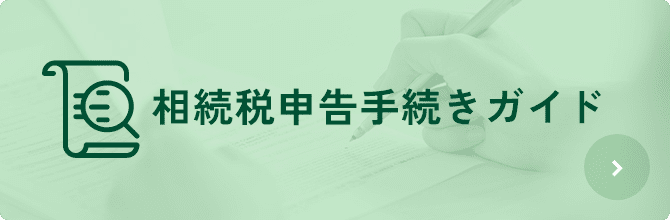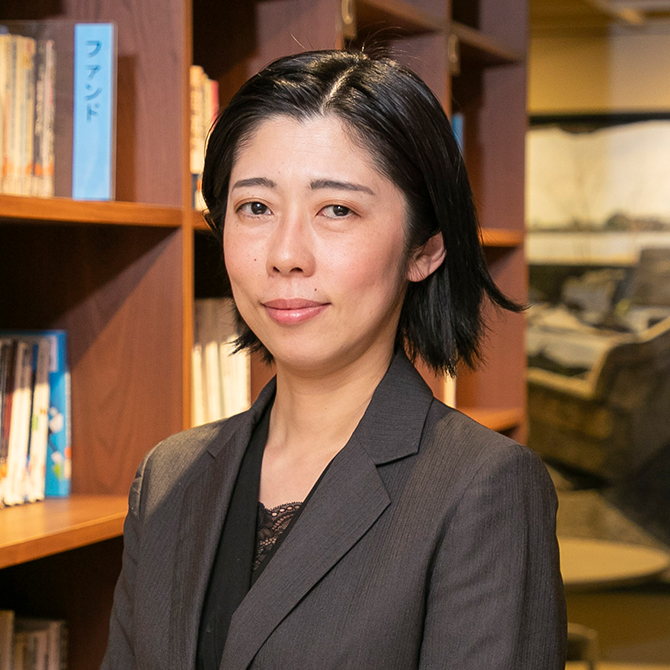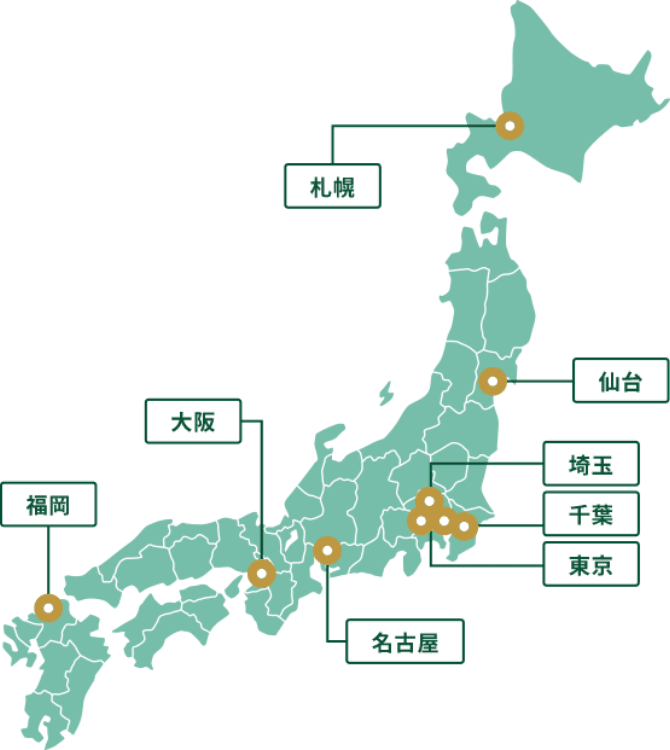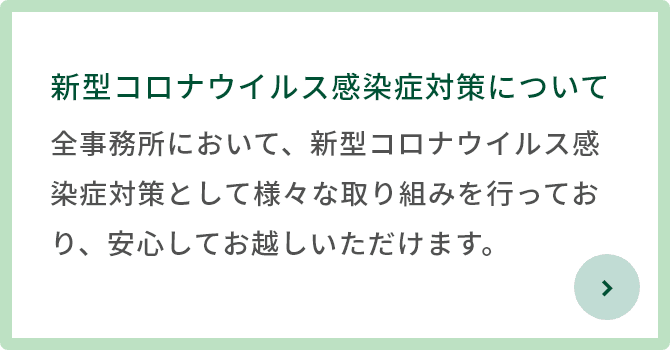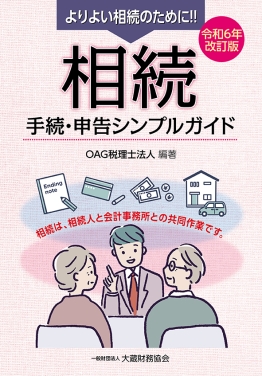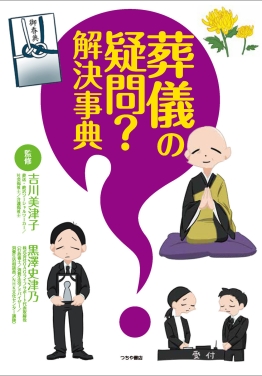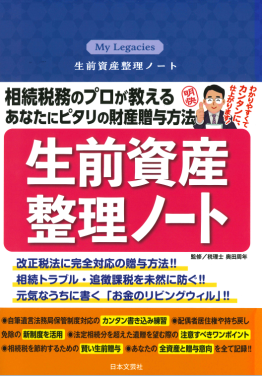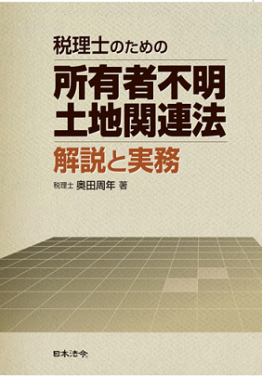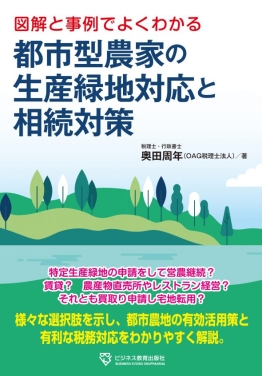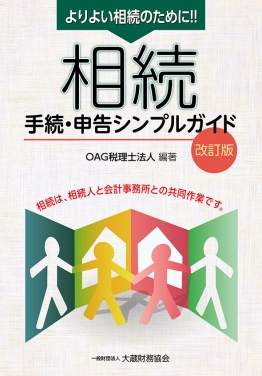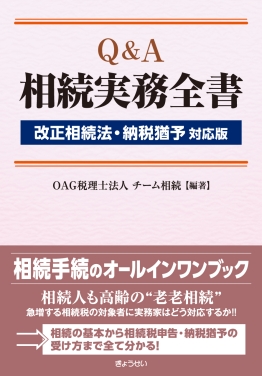column
相続コラム
相続に関する役立つ知識を解説しています。
about
「税理士と国税OB」の視点での
卓越した相続サポートで
最良な選択へ導きます
国税OBは、税法や税務審査のプロセスを深く理解しているので、
確実な法令遵守の上で最良の相続税申告を実施できます。
相続税申告は、不動産の評価や事業承継、海外資産の扱いなど、
難易度が高い課題も多いです。そのような課題も国税OBであれば、
国税庁での経験と豊富な知識を活かし、適切に対応することが可能です。
複雑な相続であっても必ずお客様をベストな選択へ導き、
最良の相続税申告を行います。